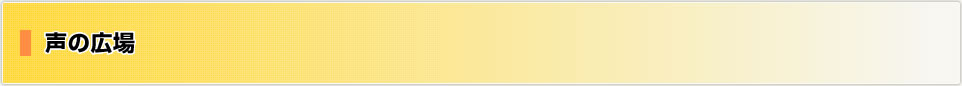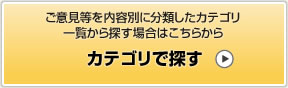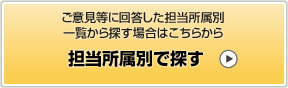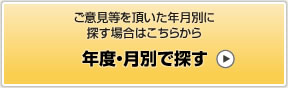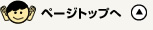福岡県では、県政の効率的かつ合理的運営を進めるために、県民の皆さんからのご意見、ご提案をお聴きしています。
-
受付日 :2024年12月3日
学校の呼び捨て文化について (カテゴリ:教育・文化/教育) -
子どもが中学生です。1学期、2学期と担任と面談する機会がありました。
担任が生徒を「太郎は」のように呼び捨てにしてるのが気になります。
保護者の前でもやるのだから担任本人はそれが良くないことだとは考えていないのが伺えます。
保護者の前だからと取り繕わない姿勢については肯定的に評価します。単純に、生徒を呼び捨てることを学校や行政はどう考えているのかが知りたいです。
「太郎君は」と「太郎は」で、後者の呼び捨て文化の方が距離が縮められてよいとする教師が居るのは存じています。一方で、必ず「さん」を付けるという教師も居ます。
教育委員会や学校管理職としてはどう見ているのでしょうか。学校現場に呼び捨て文化が存在することに関知せず、それがあるとしても教師個人の見解に委ねられているという状態なのでしょうか。
呼び捨ては良くないという気持ちではなく、生徒をどう呼ぶか統一されてない感じが不思議です。
貴重な御意見ありがとうございます。
児童生徒の呼び方について、県教育委員会として教職員に統一した指導は行っておりません。
児童生徒は、日々の生活の中で、教師が意図する、しないに関わらず、教職員が児童生徒に対してどういう態度で接しているか、何か問題が起きたときにどのような言動をとっているのかを見ながら、たくさんのことがらを学び取っています。学校や学級のその場の在り方や雰囲気といったものが、児童生徒の豊かな人権感覚育成に大きな影響を及ぼしていることを、全教職員がしっかりと認識しておくことが重要だと考えます。
県教育委員会としましては、今後も学校の教育活動全体を通じた人権教育の推進に努めるとともに、児童生徒一人一人が自分が大切にされていることを実感できる学校づくりを目指してまいります。
教育庁 人権・同和教育課